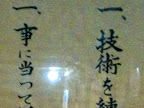以前の記事の最後に、札幌市下水道の鉄蓋を載せました。「札」の文字がおかしいんじゃない?というものです。 図1、図2に改めて写真を掲載します。
 |  |
| 図1:札 | 図2:札(?) |
写真左側が、ごく普通の「札」=木+乚です。対して写真右側の蓋に記されている文字は、木+ヒになっています(以下、日本語の文字としてはこれを木ヒと略記します)。
このことに気がついた時、最初に思ったのは「これは誤字じゃないの?」ということでした。こんな字は見た事ないし、札幌といえば木+乚しかありえないと思ったからです。
一方で、本当にこんな漢字があるのか?という疑問もあり、調べてみたところ有りました。
朼です。これはユニコードでU+673Cと定義され、読みは北京語でbi3です。
康煕字典や
宋本廣韻にも見えます。意味は祭祀の際に牲を載せる台か何かです(多分)。詳細は
漢典で確認できます。日本語としての音訓は無く、日本では使用されていない漢字ですが、少なくとも文字としては存在することが分かりました。また現代の中国語圏では、札幌と表記する際に「
朼」を使うこともあるようです。
しかし、それでも疑問は残ります。何故この字なのか。サッポロを札幌と書くのは音写であり、漢字の意味によって選択されたのではありませんが、かといって音写でも木ヒを選択する理由はないと思います。また、誤字にしてもあまりに堂々としているし、近年設置されたと見られるコンクリート製蓋にも木ヒが記されています。
 |
図3:『特殊汚水桝設置図』より
部分拡大 |
さらに、札幌市が公開している「特殊汚水桝設置図」(
PDF)を確認すると、木ヒで示されていることが分かりました(図3)。やはり、積極的に木ヒを用いていると言えます。
これはいったい何なのか。
考えていても埒があかないので、勇気を出して札幌市役所に問い合わせてみました。
担当課の方からいただいた丁寧な返答(ありがとうございました)には、「
旧漢字(由来は
中国新字体)をデザイン化した
意匠文字」というものでした。ふむふむ……え? 旧漢字? 中国新字体というのはおそらく現行の「
朼」を指すものと思われますが、「札」に「旧漢字」があるというのは初耳です。また、大正期にこの字の使用がみられるということなので、重ねて典拠を問い合わせた所、またも丁寧な返答(本当にありがとうございました!)をいただきました。手元にある事例として『新らしい札幌市の地圖』という文献をご紹介いただき、調べてみると幸いにも
日文研の
近世・近代都市図データベースで画像が公開されていました。当該部分を拡大し、赤い丸で囲んで示したのが図4です(これは大正期ではなく昭和6年の版ですが、今回の場合は版の違いは問題にならないと判断します)。
 |
図4:『新らしい札幌市の地圖』より
部分拡大、赤丸は筆者による |
こ、これは……
筆押さえではないでしょうか? 確かに堂々とした一画のように描かれていますが、私はこれはあくまでも筆押さえ、すなわち装飾であり、文字としての一画ではないと思います。
ここで札幌市役所からいただいた回答に戻ると、「意匠文字」という言葉があります。おそらく、意匠文字というのはデザインした字形を指していて、この場合は筆押さえの部分を一画として「札」に追加したのだと解釈できます。ただ、追加した場所が、図3では乚の書き出し部分に付いているのに対して、図2の蓋ではヒのように位置が下がってしまい、また実際に中国に「
朼」という文字があることに気がついてしまったためにこれを「由来」として根拠付けに採用した――これが木ヒの真相ではないでしょうか。
整理すると、以下のようになります。
- 図2の木ヒは「意匠文字」である
- この文字は「旧漢字」を「デザイン化」した
- また、その「旧漢字」は中国の漢字を「由来」とする
- しかし「旧漢字」とされている字形は、実際には元々の「札」の文字の筆押さえの部分を一画と誤解したものである
- 仮に筆押さえを一画と考えると、中国の漢字「朼」が(少々字形は違うものの、おおむね)該当する、とみなされた
- かくして図2の蓋の文字が「デザイン」された
繰り返しになりますが、この木ヒは「意匠文字」であり、デザインされたものです。従って、実際の文字と違っていてもそれが意図されたものであり、つまりこれはこれでよい、ということになります。それに異を唱えるつもりはありません。ただ、図1のように普通の「札」も併用されており、やはり個人的には違和感が否めないのです。これが図4のような筆押さえとして表現されていれば、まだ納得できるのですが……。
 |  |
図5:『札幌市鳥瞰図』より
部分拡大 | 図6:『唐尹尊師碑』より
部分拡大 |
「たまたま図4だけこの書き方なんじゃないの?」という指摘があるかもしれないので、念の為に他の事例として図5と図6を示します。図5は『札幌市鳥瞰図』(昭和11年)の部分拡大で、図4と同じく日文研で公開されています。図6は、京大の
拓本文字データベースに収録されている『
唐尹尊師碑』に見られる「札」ですが、ここにも筆押さえが見られ、唐の金石文でも筆押さえが表現されていたことがか確認できます。
また、「札」の「旧漢字」(ここではとりあえず「昔に使っていた、今の文字とは異なる字形」と理解しておきます)が「
朼」であるか否かについては、康煕字典などで意味が異なる別の字として掲載されており、日本での「
朼」の使用例も管見の限り見いだせないことから、私は「旧漢字」ではないと考えます。
<
――ここから追記:2011.11.08――>
……と、昨日書いて満足したのですが、昨晩布団の中で「
近代デジタルライブラリー」を調査していないんじゃないか?」と、私会議でダメ出しされてしまったので、近デジで「札幌」をキーワードとして引っかかる文書を総めくりしてみました。総めくりといっても全ページを見たわけではなく、外題や内題、奥付、あと本文の活字など要所要所を眺めただけです。基本的に活字としては木ヒは存在しないだろう、しかし表題などには文字の装飾があり得る、といういうのが理由です。
 |
図7:『貨物掛必携』昭和14年 表紙部分拡大
|
 |
| 図8:『北海道案内』昭和13年 表紙部分拡大 |
その結果、なんと木ヒを発見してしまいましたΣ(゚д゚lll)
図7は『貨物掛必携』、図8は『北海道案内』、ともに札幌鉄道局の編纂によるものです。図7は、明らかにヒに作られていて、図2・図3の木ヒと殆ど同じといってもいいくらいです。図8は、図5にみられる筆押さえが僅かに下がった形で、この僅かな違いが筆押さえを一画に変化させています。いずれも表紙に掲載された、デザインされた字形です。なお本文活字はいずれも「札」につくられています。ざっと確認しましたが、木ヒは表紙以外にはみられません。
もしかしたら、他にも札幌市や関連する公共機関などで、大正~昭和期にこのような木ヒの事例が見つかるかもしれません。本文活字ではなくデザインされた字形である以上、これはあくまでも木ヒであって「
朼」であるとは考えられませんが、当時のこうしたデザイン事例が図3の文字デザインに反映された可能性があります。
結論としては、「
もともとは筆押さえであった要素が、大正~昭和期にはあたかも一画のように扱われ、デザインとしての字形に影響を与えた結果、汚水桝の木ヒが生まれた」と考えます。「旧漢字」という「由来」の根拠の是非はさておき、実際にみられた字形を参考にしたデザインという意味では、札幌市役所からいただいた回答が裏付けられたといえます。
<
――ここまで追記:2011.11.08――>
それにしても、文字デザインの奥深さと漢字の面白さを、再認識しました。また、現行の仕様にみられる木ヒの由来については、ひとまずスッキリしました(´∀`*)
間違いなどありましたら、ぜひご指摘ご教示いただければ幸いです。